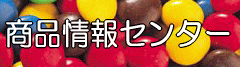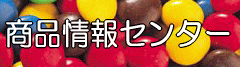|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五月病とは − 五月病は環境の変化による一時的なもの −
|
学校や職場、転居などで環境が変わり、最初のうちは張り切っていたのに、5月の連休明け頃から、なんとなく気分が落ち込む、疲れやすい、勉強や仕事、家事などに集中できない、眠れない、などといういう人が少なくありません。
これがいわゆる「五月病」(Freshmen’s syndrome)です。
五月病とは元来、大学入学後の学生が、5月連休明け頃からうつ的気分にみまわれ、無気力な状態になる事からついた病名です。
近年では、学生の五月病は減っているようですが、それに代わって新社会人に同様の症状が見られることが増えています。
新社会人の場合は、新人研修などが終わって実際の仕事をはじめた後の6月頃に症状が出ることが多いため、新五月病または「六月病」と呼ばれています。
最近では低年齢化がみられ、小学生〜高校生にも五月病といえる症状がみられるようになってきています。
実際は5月の連休明けだけでなく、長期休暇(夏休み・冬休み・春休み・お盆休み・正月休みなど)明けにも多くみられます。
年間を通して抑うつ、無気力の症状を訴える事が多くなってきており単なる季節病ではなくなってきています。
五月病という言葉は皆さんご存知のように広く知られた言葉ですが、実は医学用語ではなく、決まった概念や定義があるわけではないのです。
これは環境の変化への不適応現象で、多くの場合は一過性の症状と考えられています。
「退却神経症」ともよばれ、その人の本業からの退却と社会不適応状態をも含んだ概念であり、単に五月病と呼ばれている以上の広い概念だといえます。
ただ中にはアパシー症候群や適応障害とされる場合もあります。
免疫の働きが低下して病気に罹りやすくなったり、ストレスをためすぎて心筋梗塞や消化性潰瘍、感染症、精神科疾患(うつ病など)にかかる率が高くなります。
五月病は完璧主義で物事にこだわりがちな人や、内向的で孤立しやすい人、過保護に育てられた人などが五月病になりやすいといわれています。
○真面目に物事を考える優等生タイプ
○几帳面で完璧主義
○内向的で孤立しやすい
○勤勉で周囲に気を使いすぎる
○過保護に育てられた人
つまり、新たな環境に適応できずに、そのことへのあせりがストレスになり、"何とかしなければ"と思えば思うほど、深みにはまってしまうわけです。
疲れているのに眠れない、食欲や性欲も減退し、皆にとけこもうとするがうまくいかずに自己嫌悪に陥り、そのまま放置しておくと、最後には死んでしまいたいなどと考えてしまいます。
このような本当のうつ病にまで進展しないうちにきちんと治療を受ける事が重要です。
新しい環境での生活というものは、著しい変化が1度に降りかかり、肉体的にも精神的にもくたびれてしまいます。
4月は新しい生活にいち早く慣れることや友達作り、好奇心や期待で胸がいっぱいだったのに対して5月に入ってこれらがストレスという形となって、体や心の重荷となっていくのです。
また、本人の性格も重要な因子で、同様のストレスがかかっても、それが非常に負担になる人もあれば、上手く乗り越える人もいるわけです。
○ 初めての一人暮らしや時間の使い方の変化など、新しい環境についていけない
○ 新しい人間関係が思うようにいかない
○ 入試・入社といった大きな目標を達成した解放感
○ 大きな目標を達成したことにより、次の目標を見失ったり、混乱したりする
○ 想像していた新生活と現実のギャップについていけない
症状は身体的には頭痛、めまい、肩こり、動悸、朝起きにくい、疲れやすいといった自律神経症状で、時に過呼吸発作(過換気症候群)がみられることもありますが、もちろん内科的には異常はみられず「目律神経失調症」などと診断されることが多いようです。これらの身体症状に加え、気分が落ち込む、イライラ感、決断力や思考力の低下、気力の低下、食欲低下や睡眠障害が起こってくる場合もあります。
| <<主な症状>> |
| 身体的なもの |
精神的なもの |
| 疲れやすい |
やる気が出ない |
| 朝起きられない |
イライラする |
| 食欲がわかない |
なんとなく落ち込んでいる |
| めまい |
何をするのも面倒で億劫 |
| 頭痛/腹痛/便秘 |
興味・関心がわかない |
| 不眠 |
思考力・判断力が持てない |
| 動悸 |
不安や焦りを感じる |
|
| 免疫力低下 |
感染症にかかりやすくなる
風邪 水虫 ヘルペス カンジダ など |
| 自己免疫疾患 |
膠原病 アレルギー がん |
| 循環器 |
脳卒中
心臓病(狭心症・心筋梗塞・心房細動など)
高血糖
高コレステロール
高血圧
血栓 |
| 消化器 |
消化性潰瘍(胃潰瘍・十二指腸潰瘍)
大腸ポリープ
神経性下痢
神経性胃炎 |
| 自立神経失調 |
睡眠障害(入眠困難 中途覚醒 多夢失眠)
頭痛
めまい
動悸 |
| 精神疾患 |
うつ病(感冒症状 消化器症状) |
五月病になってしまったら、次のような方法を試みると、大抵の場合、1〜2ヵ月で自然にその状態から脱することができます。
○趣味やスポーツでストレスを解消
○たっぷり寝る、ゆっくり休む
○ゆっくりお風呂に入る
○好きな音楽を聞く
○アロマテラピーでリラックスする
○映画や絵画展、コンサート、小旅行などに出かけて気分転換を図る
○新しい目標を見つける
○友人や先輩などに、話を聞いてもらう
○カウンセリングを受ける
○他に好きなことを見つける
以上の対処法は、五月病の予防法でもあります。環境が変わったりしたら、五月病になる前にこれらの方法で心身をリラックスさせるとよいでしょう。
まずはストレスによる心の治療にあたる心療内科や精神科で診てもらうことです。
以前は、受診に対し心理的な抵抗もあったようですが、最近はこれらのクリニックも増え、特に若い人は抵抗なく受診されるようになりました。
治療方法は人によって違ってきます。カウンセリングやライフスタイルヘのアドバイスのほか、時には抗不安剤(安定剤)や軽い抗うつ剤を服用していただく場合があります。
五月病を改善するには、イライラを鎮める働きがあるカルシウムや、カルシウムの吸収を調整するマグネシウムがおすすめです。
マグネシウムは、ナッツ類や大豆、ひじきなどに多く含まれています。
ほかに、ストレスを和らげる働きがあり、ごまなどに多く含まれるトリプトファン、体の調子を整えるビタミンCなどを摂りましょう。
暴飲暴食やタバコを控えることも大切です。
| <<ストレス対策におすすめの栄養素>> |
| 栄養素 |
理由 |
多く含まれる食品 |
| カルシウム |
神経の興奮を抑えて精神を安定させる |
牛乳、乳製品、小魚、ひじき |
| マグネシウム |
ストレスが溜まると吸収が悪くなるため、意識して摂りたい |
大豆、カシューナッツ、納豆 |
| トリプトファン |
ストレスをやわらげる |
ゴマ、大豆、卵黄、牛乳 |
| ビタミンB1 |
神経疲労の軽減に役立つ。不足すると、イライラしがちで精神状態が不安定になりがち |
豚肉、ウナギ、カレイ、落花生、シイタケ、玄米 |
| ビタミンB6 |
不足すると、疲れやすく、食欲不振に |
玄米、そば、ブロッコリー、バナナ、キウイ、パイナップル、イチジク |
| ビタミンC |
ストレスを解消するために使われる栄養素 |
イチゴ、レモン、ピーマン、大根、ホウレンソウ、キャベツ、サツマイモ |
一口にお風呂(入浴)と言っても、どんな効果を求めるかによって入浴方法が異なってきます。
朝の目覚めが悪い時や気を引き締めたい時は、高温浴がおすすめ、逆にリラックスしたい時や夕方・寝る前には、微温浴がおすすめです。
| 温浴区分 |
温度 |
効果 |
| 高温浴 |
42℃以上 |
交感神経に優位。心身を目覚めさせる。緊張状態を高める。脈拍数が増え、血圧上昇。 |
| 中温浴 |
39〜40℃ |
体温より少し高い温度。血液の循環をよくする。 |
| 微温浴 |
37〜39℃ |
副交感神経に優位。筋肉がゆるむ。脈拍数が減り、血圧低下。心身をリラックスさせる。 |
| 低温浴 |
34〜37℃ |
体温と同じ温度。血圧や脈拍に変化がなく、負担が少ない。カロリーの消費も少ない。 |
| 冷水浴 |
24〜34℃ |
プールの温度。サウナなどで火照った身体を冷やすのに最適。 |
| 不感温浴 |
24℃以下 |
冷たく感じる温度。
|
注意事項 ※食事の直前・直後、飲酒後の入浴は避けましょう。
※お風呂の前後には、必ず水分補給をしましょう。
入浴剤やアロマオイルを使ってお風呂の演出をしてみましょう。
色と香りはリラックスしたり、やる気を出したりするのにとても効果があります。
身体が温まるだけでなく、よい香りや色が鼻や目から脳に伝わり、心身ともにリラックスできます。
また入浴剤だけでなく、音楽をかけたり、浴室の照明を消してローソクを灯すのも効果的!
心地よい音楽やローソクの炎が心を落ち着かせ、眠りに誘います。入浴は快眠にも効果的なのです。
| 色の効果 |
| レッド |
エネルギッシュ、攻撃的、気力向上、食欲増進 |
| ピンク |
幸せな気分になれる、恋愛向き |
| オレンジ |
リフレッシュ、健康的 |
| イエロー |
ビタミンカラー、元気、前向き、やる気が出る |
| グリーン |
心を落ち着かせる、目にやさしい |
| ブルー |
心を静める、疲労を和らげる、食欲減退 |
| パープル |
リラックス |
| 香り(アロマオイル)の効果 |
| 落ち込んだ時、悲しい時 |
オレンジ、パイン、グレープフルーツ、ジャスミンなど |
| ストレス・イライラや不安を感じる時 |
グレープフルーツ、ジャスミン、ラベンダー、バジルなど |
| 集中力を高めたい時 |
ペパーミント、レモン、ローズマリー、コリアンダーなど |
| 眠れない時 |
オレンジ、ラベンダー、ローマンカモミールなど |
※これ以外にも、よいエッセンシャルオイルはあります。
セラピーを受けるときにはセラピストに相談してみましょう。
労宮(ろうきゅう)という手のひらの中央のくぼみを押すと眠気、精神の疲れがとれるそうです。
頭のてっぺん。体がリラックスできるつぼだそうです。
入ったばかりなのにやる気が見えない、ボーッとしている…。
こんな家族や部下を見ると、つい「がんばれ!」なんて声をかけたくなるものですが、これは禁句です。
がんばっているのに慣れられない、なかなかついていけないところに五月病・六月病の原因があるからです。
部下や家族が五月病・六月病のようだと感じたら、まずは怒らない・励まさない。
もちろん、ナマケモノだとか根性がないなどと責めるのも厳禁です。
そして、よく話を聞いてあげましょう。
話をしている間に、本人は気持ちが軽くなるし、問題点も自覚していくようになります。
また、「仕事ができる!」という自負を持って入社したのに、現実は思うようにいかずに悩んでいるような部下の場合は、コミュニケーションを増やして小さな目標を見つけて仕事に取り組むよう誘導してあげるといった配慮も大切です。
要は、五月病・六月病の状態を、よくわかってあげること。
それともうひとつ大切なことは、症状が進んだり、うつ病へと移行させないためにも、症状が重いときや長引いているときは、できるだけ早く病院へ行かせることが必要です。
周囲から見れば、誰にでも多かれ少なかれあることでも、当人にとっては大変な時期。
ゆっくり待ってあげる時期だと思って、暖かく見守ってあげましょう。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|