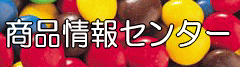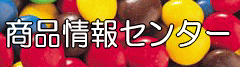|
|
|
|
|
|
|
<薬物療法>
花粉症と診断された場合、まず、薬物療法が選択されるケースが多いでしょう。予防的に使うと効果の高い薬、既に出ている症状を抑える薬、点鼻薬、点眼薬など、それぞれ症状に合わせて使用が考慮されます。
<減感作療法>
アレルギーを起こしやすい体質を変える根本的な治療法として行われています。簡単にいうと、アレルギーを引き起こす抗原を少しづつ体内に入れることで、体に抵抗力をつけさせようとする治療法です。減感作療法は症状がひどい人や、通年性のアレルギーを併せ持つ人、薬物療法がうまく適応しない人などへの実施が考慮されます。スギ花粉症への有効率は65〜75%程度とされています。
<レーザー手術>
鼻づまりの原因を取り除く外科的手術も行われています。その中で、最近、よく話題になるのがレーザー光線を腫れた粘膜に照射する治療法です。但し、アレルギーが治るわけではなく、症状を抑える目的で実施されます。
|
|
|
|
|
|
<早めの治療開始と症状に合った薬を選択>
花粉症治療の薬物療法は、予防段階から始める抗アレルギー薬の内服を基本とし、症状に合わせて点鼻薬と点眼薬を使う併用療法が、多くの患者さんで良い結果を残しています。また、花粉症の薬は薬局で販売しているものより医師の処方によるものの方が効果があり眠気等の副作用が少なくなっています。
抗アレルギー薬は花粉が本格的に飛散する2週間前からの服用が効果的です。早目に医師の診察を受け薬の服用を開始することが、花粉症の発症を遅らせて大量飛散時期の症状を軽くするために大切です。軽い花粉症の場合は、基本的に抗アレルギー薬を服用。症状がひどい時のみ即効性のある第一世代抗ヒスタミン剤を頓服で服用することもあります。
鼻水・くしゃみ・鼻詰まりなどの症状がひどい場合には、抗アレルギー薬を基本的に服用し、大量に飛散している時には局所ステロイド薬(点鼻薬)を併用します。内服のステロイド薬(セレスタミンを含む)は、本当に症状の重い時期のみ2週間を限度としそれ以上は服用しない。また、漢方薬も体質改善や症状を和らげる目的で使用されることがあります。
<眠気の副作用は個人差がある>
花粉症の治療薬は、眠気・口渇などの副作用がありその発現や強さは人によって非常に差があります。数ヶ月間に渡って服用することになるので一度処方された薬が合わないからとあきらめずに、副作用の状況などを医師に伝えて自分にあった薬を見つけることが大切です。一日一回服用の薬もあります。
|
|
|
|
|
|
<花粉シーズンの前から>
抗アレルギー薬は肥満細胞からヒスタミンなど化学伝達物質が放出するのを抑える作用があります。また放出されてしまったヒスタミンに対して抗ヒスタミン作用のある薬(第二世代抗ヒスタミン薬)とない薬があります。抗ヒスタミン作用を持つと効果が強い反面、眠気・口渇などの副作用が出やすいといわれています。
花粉が飛び始める2週間前から予防的に飲み始め、飛散時期が終わるまで飲み続けるのが効果的です。最近では、眠気の副作用の少ない薬が開発されています。服用回数も1回のものと2回のものがあります。自分の症状と副作用の発現の程度を医師に伝えてご相談下さい。内服薬のほか、点鼻薬、点眼薬にも幅広く使われています。
抗アレルギー薬は、内服薬のほかに、点鼻薬・点眼薬にも幅広く使われています。
|
|
|
|
|
|
どのような日に花粉が多いのかを知っていれば、可能な限りその時の屋外にいないように工夫が出来ます。まずは、インターネットの花粉飛散予報で今日の花粉量を確認。心の準備も万全にしましょう。
<花粉が多く飛ぶ日>
・ 晴れて気温が高い日
・ 乾燥して風が強い日
・ 雨の日の翌日で晴れた日
雨で地面に落ちていた花粉が一気に舞い上がり、二日分の花粉が飛散する恐ーい日です。
<花粉が多く飛ぶ時間>
・ 日が上り、気温が上がってくるとスギの雄花が開花し始め、やがて街に飛散し始めます。お昼前後に飛散量が最大になるので外出には注意を。
・ 夕方、日がかげり気温が下がってくると、上空まで飛散していた花粉が地上まで下がってきます。そのために再び、花粉量が増加します。
|
|
|
|
|
|
花粉対策の備えは万全ですか?忘れ物はありませんか?お出かけ前にもう一度チェック!
<マスク>
マスクには、価格の安い普通のガーゼで作ったものから、0.1ミクロンの空中微粒子までもカットする使い捨てのものまで色々とあります。(スギ花粉の大きさは30〜50ミクロン)
1日外にいなければならない日には細かい粒子までもカットするマスクが欲しいですね。その日の行動や花粉飛散状況によって使い分けると良いでしょう。
<メガネ>
目の粘膜に花粉を付けないのが一番ですから、予防にはやはりメガネです。サイドにガードが付いている花粉症専用のメガネや、最近はおしゃれなサングラスタイプも発売されています。もちろん、専用メガネじゃなくても、普通のメガネでもかなりの効果があります。
<帽子・洋服とヘアスタイル>
髪に花粉をつけないために、お出かけには必ず帽子の着用を。帽子の素材もさらさらと花粉が落ちそうなのがお勧めで、花粉が付きにくい帽子というのも発売されています。
帽子と同様に、上着もさらさらと花粉が滑り落ちそうなのがお勧めです。ウールや毛皮の素材は花粉がつきやすいので避けた方が賢明です。とにかく、外で浴びた花粉を屋内に持ち込まないことが大切です。
|
|
|
|
|
|
<まず家に入る前に>
玄関の前で、上着・帽子を取り、しっかりはたいて花粉を少しでも家に入れないように。洋服ブラシなどを使うとよいですね。そして、上着・帽子は玄関において部屋に入りましょう。
花粉症の本人だけでなく、家族のみんなにも協力してもらいましょう。
<とにかくすっきりと>
やはり帰宅後は、少しでも早くすっきりしたいですよね。お風呂に入って、顔も髪もきれに洗いましょう。うがいもお忘れなく。鼻も丁寧にかんで外で吸いこんできた花粉を少しでも追い出しましょう。
<目を洗う>
最近は、目を洗うための製品が多く発売されています。使用するのはお風呂上りのきれいな時にしましょう。くれぐれもマスカラたっぷりの状態で使用しないでください。かえって、まつげに付いた花粉やゴミが入ってしまいます。
|
|
|
|
|
|
室内の対策は、やはり空気清浄機で室内の花粉を取ってしまいたいですね。最近は色々な空気清浄機が発売されています。
<空気清浄機選びのポイント>
・ 使用する部屋の大きさに適したものを選ぶ。
・ 部屋を閉め切った状態で使用する。すきま風は塞ぐようにしましょう。
・ 室内に入ってきた花粉は、たいてい床に落ちています。ですので、下のほうに設置した方が効果的。
・ 最近は、自動で花粉などを検知して清浄力を調節するものがあります。自動でないものは、花粉の時期には「強」で使用しましょう。
・ エアコンに強力な空気清浄機機能が付いたものもあります。エアコン買い替えの時には検討してみてください。
<お酒とたばこ>
花粉症の時期には、のどや鼻の粘膜が過敏になっています。タバコは、粘膜に刺激を与えるので控えた方がよいでしょう。また、お酒を飲むと血管が拡張して鼻づまりなどがひどくなる場合があります。
<アルコールと薬との相互作用>
花粉症の飲み薬には、眠気の副作用があることが示すように中枢神経系を抑える働きのあるものがあります。抗アレルギー薬・抗ヒスタミン薬には、アルコールと一緒に服用すると眠気が強く出たり、注意力が散漫となるものがあります。自分の飲んでいる薬はどうなのか、あらかじめ医師・薬剤師に確認しておいてください。
<眠る時は>
少しでも花粉のない状態で眠るのはいうまでもないですが、鼻づまりが強くて眠れない時には鼻腔を広げるテープを利用してみましょう。爽やかなメントールの香りの付いたものもあります。
<寝不足にご注意>
花粉症の時期に、ストレスがたまり寝不足になると症状が強く出る場合があるので、規則正しい生活を心がけましょう。もちろん、風邪も花粉症を悪化させる原因となります。
|
|
|
|
|
|
その効果の裏側には、1ヵ月以上もステロイドの影響を受け続けることによる副作用の可能性も忘れてはいけません。実際に、最近ではその高率に発生する副作用により、ほとんど行われない治療法になっています。
<ステロイドの副作用>
免疫力の低下・骨粗しょう症・生理不順・ムーンフェイス・むくみなど。
<花粉症の治療におけるステロイド>
ステロイドの点鼻薬は局所に限る治療なのでほとんど副作用はありません。内服薬(主にセレスタミン)のステロイドは、漫然と長期間に渡って使用せず、症状のひどい時のみに使用されています。
|
|
|
|
|
|
<花粉飛散日の2週間前から目薬を>
早めの花粉症対策に、薬物を使う『初期療法』があり、花粉飛散日の2週間前から抗アレルギー薬の服用を始めることがすすめられています。この療法により、アレルギーの発症時期を遅らせ、シーズン中の症状を軽くすることができるとされています。
この2週間前という期間は2つの意味があり、抗アレルギー薬は、服用して2週間後ぐらいから効くことが多いということ、飛散シーズンの幕開けである飛散開始日の2週間程度前に、すでに花粉が飛びはじめる初観測日をむかえているということがあります。
つまり目の痒み、充血といった花粉症の症状も、花粉飛散日の2週間位前から目薬を使い、花粉症による腫れを抑え、アレルギー反応を起こりにくくすることができるといわれています。しかし、症状と効果の現れ方は、体質など個人差もありますので、眼科医や薬剤師に相談し、目薬の処方を受けましょう。
<花粉防止グラスで花粉をブロック>
今年の花粉飛散予想を聞く限り、目に入る花粉をブロックするグラスやゴーグルを購入することも検討事項のひとつかもしれません。花粉防止グラスは、透明または薄い色合いのプラスチック製で、サイドからも花粉が侵入するのを防ぎ、両目を保護するようになっています。サイズ展開がある場合もありますから、購入時には、フィット感を確かめましょう。
また、花粉防止グラスが大げさだと思う方には、レンズ部分がカーブしていて顔にフィットする花粉カットグラスや一般のサングラスを装用してはいかがでしょうか。何もしないで外出するよりは、目にやさしい花粉飛散時の新習慣といえるでしょう。
<コンタクトレンズは要注意>
この時期、コンタクトレンズをお使いの方は、注意が必要です。アレルギーの原因となる花粉がレンズに付着してしまい、症状が強くなりやすく、痒みや充血に悩まされ続けます。また、目の痒みがひどいと、ついつい手でこすってしまいがちですが、その際にレンズで角膜を傷つけてしまう危険性もあります。
ですから、花粉症の時期はできるだけコンタクトレンズ装用を控えたり、代わりにメガネをかけるといった工夫が必要かもしれません。目が痒いときは、目薬を使う、目の周りを冷やすなどして目に直接手で触れるのはやめましょう。
|
|
|
|
|
|
<たっぷり睡眠をとりましょう>
花粉症によるストレス対策としておすすめしたいのが、十分な睡眠です。睡眠は、自律神経の安定化のためにはもっとも大切な方法のひとつ。日ごろ疲れがたまっているなと思ったら、意識して睡眠時間を確保するよう努めてみましょう。
睡眠中は、その時間だけでも不快な花粉症の症状を忘れることができますし、イライラした気分もすっと落ち着かせてくれます。ただし寝具は外に干さないよう注意を!睡眠中まで、花粉の害にさらされないようにしましょう。
<運動はストレス解消&症状の悪化防止につながる>
ストレスがたまりすぎると、花粉症の症状もますます悪化します。悪化防止のために特に心がけたいのが、適度な運動です。運動によって体力をアップさせ、自律神経を鍛えることが、花粉症に負けない体づくりにつながることが多いようです。また、血行がよくなることで、鼻づまりも改善することが多いようです。
ただし、外で行う運動は花粉にさらされる時間を増やしてしまいますので、この季節はインドアの運動がおすすめです。好きなものを選んで上手なストレス対策&体力づくりに取り組んでいきましょう。
|
|
|
前のページ | 1 2 3 4 | 次のページ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|